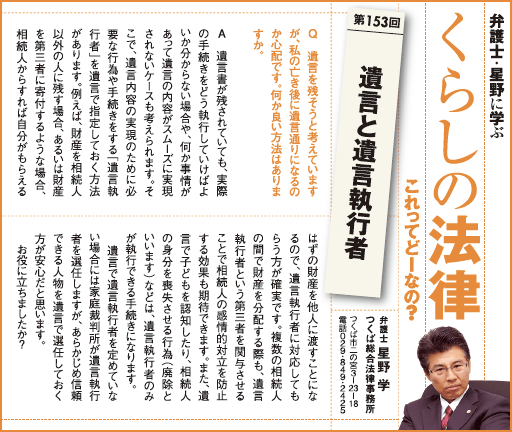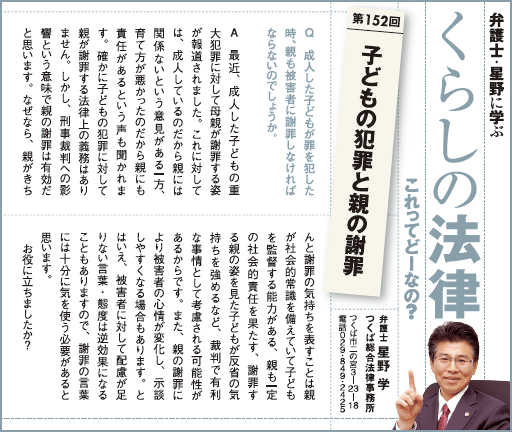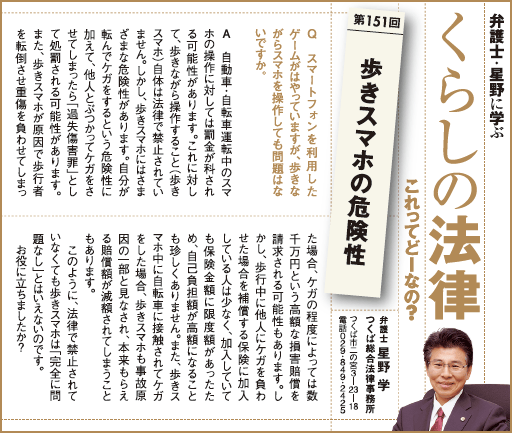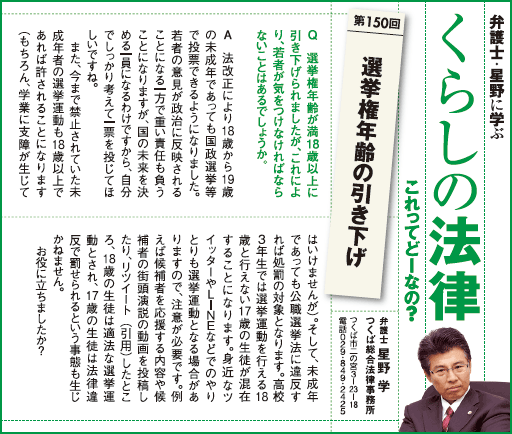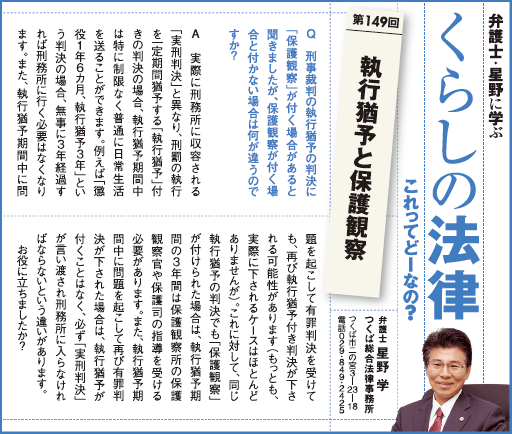Q
遺言を残そうと考えていますが、私亡き後に遺言通りになるのか心配です。何か良い方法はありますか。
A
遺言書が残されていても、実際の手続きをどう執行していけばよいか分からない場合や、何か事情があって遺言の内容がスムーズに実現されないケースも考えられます。
そこで、遺言内容の実現のために必要な行為や手続きをする「遺言執行者」を遺言で指定しておく方法があります。
例えば、財産を相続人以外の人に残す場合、あるいは財産を第三者に寄付するような場合、相続人からすれば自分がもらえるはずの財産を他人に渡すことになるので、遺言執行者に対応してもらう方が確実です。
複数の相続人の間で財産を分配する際も、遺言執行者という第三者を関与させることで相続人の感情的対立を防止する効果も期待できます。また、遺言で子どもを認知したり、相続人の身分を喪失させる行為(廃除といいます)などは、遺言執行者のみが執行できる手続きになります。
遺言で遺言執行者を定めていない場合には家庭裁判所が遺言執行者を選任しますが、あらかじめ信頼できる人物を遺言で選任しておく方が安心だと思います。
お役に立ちましたか?